経営承継円滑化法は事業承継にどう関わる?法律の基礎およびメリットをわかりやすく解説します!
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、「経営承継円滑化法」)は、中小企業の事業承継の推進を目的とした法律・特例のことを言い、中小企業庁の主導で2008年に作られたものです。
近年では、親族や従業員以外の第三者に事業承継を行う事例が増えてきており、それに伴い、より円滑な事業承継を推進することを目的に、条文の改正が行われています。
本稿では、経営承継円滑化法によって定められる事業承継支援策の概要・適用のメリットを解説します。
目次
経営承継円滑化法の制度趣旨
経営承継円滑化法が制定された背景としては、通常の相続税法・民法の定めに基づく場合に、以下の要因によって事業承継を行おうとする後継者に対して大きな負担が掛かってしまうことが問題視されていたという点があります。
① 事業を引き継ぐにあたって生じる多大な贈与税・相続税の負担
② その他の相続人による遺留分の請求による承継した会社株式の分散
③ 株式の受贈が特別受益と認定されることによる相続上の問題
会社株式も先代経営者が保有する財産のひとつであるため、その財産を受け継ぐことに伴って生じる税金や他の相続人との協議・合意は不可避なものです。
① 贈与税・相続税の負担
相続の際の非上場株式の評価額は相続税法によって計算方法が定められています。
例えば先代経営者が一代で創立し経営してきた会社であっても、創業当時から大きく事業規模を拡大しているような場合には、相当に高い評価額が付く結果、多大な贈与税または相続税が課されるというケースも珍しくありません。
その税金負担を個人である後継者が負担することは、金銭面・精神面において難しいことは容易に想像ができると思います。
こうした直接的な金銭的理由から事業承継が進みにくいことは古くから問題視されていました。
② 他の相続人による遺留分の請求
「遺留分」とは、相続において、亡くなった被相続人の配偶者や子に最低限保障される財産相続の権利のことを言います。
被相続人にとって、本来自己の財産を誰に渡すかは自由に行えるものですが、民法上、この遺留分の制度があることによって、権利を持つ相続人は遺留分に相当する財産の相続を受けられない場合は、受贈者に対して請求することが可能です。
これを「遺留分侵害額請求」と言います。
事業承継において遺留分が問題となるのは、先代経営者と後継者との間で100%の株式を承継することの合意ができていたとしても、遺留分を持つ親族が請求権を行使する場合には、一定割合を渡さなければならなくなることです。
これによって、一部の株式は他の株式が保有することになり、それを取得しようとするとまた資金が必要になります。
また、仮に生前贈与により会社株式を受け取っていたとしても、贈与した被相続人と贈与を受けた後継者が、「贈与によって遺留分を侵害する」と知りながら贈与を行った場合には、この遺留分請求の対象となる点にも留意が必要です。
なお、遺留分に相当するのは、全体の相続財産のうち1/2の割合です(被相続人に配偶者と子がおらず父母のみが相続人となる場合は1/3)。
③ 特別受益に対する相続上の問題
「特別受益」とは、相続人の中に被相続人から生前贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の公平を図るために、生前贈与した財産の評価額を相続財産に参入して計算し、各相続人の相続分を算定することを言います。
生前贈与が特別受益とされる場合には、相続開始前10年以内の贈与が遺留分請求の対象となり、②と同様の問題が生じます。
留意すべきは、生前であれば相続に関する問題は回避できるということではなく、株式を譲り受けてから10年以内に先代経営者がなくなることがあれば、遺留分侵害額請求の対象になるという点です。
(なお、2019年の民法改正前までは、遺留分請求の対象となる生前贈与に期限がなく、10年を超えるものであっても遺留分請求が可能でした。)
経営承継円滑化法による特例措置
前述のように、法律の原則的な定めによれば、事業承継には金銭面や他の相続人との利害調整の面でいくつかのハードルがあります。
そこで、これらの課題を軽減し、事業承継を促進すべく経営承継円滑法により特例措置が置かれています。
具体的には、以下3つの施策があります。
・ 事業承継税制による贈与税・相続税の納税猶予
・ 遺留分に関する民法の特例(遺留分の除外合意・固定合意)
・ 金融支援
事業承継税制
非上場株式の相続を受ける場合に、一定の要件を充たすことで贈与税・相続税の納税が猶予される制度を「事業承継税制」と言います。
事業承継税制の適用にあたっては、会社・先代経営者・後継者のそれぞれに一定の要件が設けられています。
適用要件のポイントとしては、経営承継円滑化法に基づく認定を受けた中小企業において、会社の代表者かつ支配株主である先代経営者が、会社役員である後継者が次期代表者かつ大株主として経営に継続関与することです(後継者が親族以外であっても適用可能)。
後継者は、引き続き会社のオーナー兼代表者として継続関与することが前提となっており、仮に代表者でなくなる場合や株式の一部売却がある場合には、納税猶予は打切りとなってしまう点に留意が必要です。
事業承継税制を適用することによって、従来より大きな課題であった納税資金の確保が不要となります。
なお、当該制度は、2018年度税制改正による特例であり、現時点ではその適用期限について、2027年までとされ、適用を受けるには2023年までに会社の後継者や事業計画等について記載した「特例承継計画」を都道府県知事に対して提出することが求められています。
事業承継税制の詳細な解説についてはコチラ
遺留分に関する民法の特例
遺留分は、前述のとおり他の相続人からの遺留分侵害額請求の権利は非常に強力な法制度であるため、経営承継円滑化法においては、遺留分が事業承継を妨げることがないよう、特例が設けられています。
具体的には、一定の要件を充たすことで、生前贈与された株式を遺留分の算定から除外すること(「除外合意」)や生前贈与された株式について合意時における価格で遺留分を算定すること(「固定合意」)を行うことができます。
どちらも遺留分に対する権利を持つ相続人全員による同意が必要となりますが、事前に協議・合意を行っておくことで、遺留分が原因となる紛争や株式保有の分散を防止することができ、円滑な事業承継を進めることが可能となります。
除外合意
「除外合意」とは、先代経営者の生前に、経済産業大臣による確認を受けた後継者が、遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎となる財産から除外できる特例を言います。
遺留分権利者全員による合意取得のハードルが高いケースはあるものの、除外合意を利用すれば、会社の株式は遺留分算定の基礎となる財産の対象から外れ、それ以外の相続財産を相続人間で分割することになります。
これにより、株式に対する遺留分侵害額請求を受けることを回避することができ、事業継続に不可欠な株式の集中保有を達成することが可能となります。
固定合意
「固定合意」とは、経済産業大臣による確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額で予め固定できる特例を言います。
通常、遺留分の評価は相続の開始時点の財産の価格を基準として行います。
この取り扱いは株式に対しても同様であり、例えば先代経営者の生前に会社の株式を譲り受けた場合においては、当該株式の評価額は譲受時点ではなく、相続開始時点の価値となります。
ここで、評価を通常どおりに行うと、後継者の経営努力によって株式の価値が増加した場合、遺留分の算定はより高い評価額が基準となってしまうため、後継者にとっては不利な取り扱いとなり、事業承継の意欲を低下させてしまう可能性が問題視されていました。
このような場合に、特例の固定合意を利用すれば、相続時に株式の価値が値上がりしていても、値上がり分の相続税は考慮しなくていいことになり、後継者にとっては金銭面でメリットがあります。
遺留分の特例の適用を受けるための手続
除外合意または固定合意の特例を利用するためには、現経営者の生前に遺留分の権利を持つ相続人全員による同意が必要であり、そのためには株式以外の資産を含む公平な遺産分割案を提示し、全員の納得を得る必要があります。
合意取得後は、その内容を書面にし、1ヵ月以内に合意内容の合法性につき経済産業大臣による確認の申請を行います。
経済産業大臣による確認が済んだ後は、その1ヵ月以内に家庭裁判所に許可の申立てを行い、この家庭裁判所の許可を受けて特例の効力が認められることになります。
金融支援
事業承継時に必要となる資金は多岐にわたり、会社にとっても後継者にとっても大きな負担となります。
資金を用意できないために事業承継に前向きになれない後継者も少なくないため、経営承継円滑化法では金融支援措置を講じています。
資金調達に関する支援策として、事業承継に必要な資金を集められるように日本政策金融公庫から融資を受けやすくしています。
また、会社の代表者が変わることでその会社の信用が低下するおそれに対応するため、中小企業信用保険法の特例を適用して資金調達が行いやすくなる支援を行っています。
このような金融支援を受けるには、都道府県知事の認定が条件となります。
事業承継にあたっては、承継時だけでなく、その後にも会社の運営には資金が必要となるため、資金ショートを防ぐためにもこうした金融支援策を上手く使って経営の舵取りを行っていくことが重要です。
まとめ
事業承継の促進は、法律の改正や補助金の公募等、国の政策の中でも重要視されている分野です。
中小企業にとっては、経営承継円滑化法による特例措置が設けられていることによって、主に税金や資金面のハードルが緩和され、事業承継が進めやすい環境になってきています。
特例の制度を適用するには、複雑な要件や手続を充たす必要があるものもあるので、これらを活用して実際に事業承継を進める際には、税理士などの専門家にご相談することが良いと思います。
また、事業承継税制の適用にあたっては、経済産業省が認定する経営革新等支援機関による特例承継計画の策定が条件となっていますので、適切な知識や経験を持つ専門家へのご相談がお薦めされます。
当社はグループの税理士事務所にて、認定支援機関として事業承継の支援を行っておりますので、ご不明点等があればまずはお気軽にご相談ください。

LINE無料相談受付中!
S&Gパートナーズ株式会社はLINE公式アカウントを開設しています。
以下のQRコードを読み取っていただくか「友だち追加」ボタンを押していただくことで、お気軽に無料でご相談いただけます!
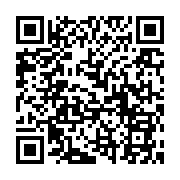
この記事を書いたのは

S&Gパートナーズ株式会社
代表取締役
税理士・公認会計士
有限責任監査法人トーマツでの勤務の後、M&AブティックファームおよびデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーでのM&Aアドバイザリー経験を経てS&Gパートナーズ株式会社および志村俊光税理士・公認会計事務所を設立。
M&Aアドバイザリー業務・財務デューディリジェンス・企業価値評価業務の経験と会計プロフェッショナルとしての知識を活かし、会計・税務の高い専門性を要するM&A取引のアドバイスを得意とする。
税理士登録番号: 144964
公認会計士登録番号: 32131



